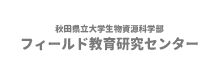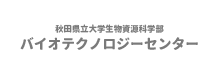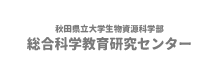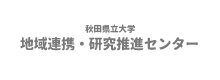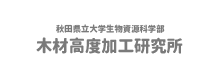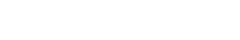教員・大学院生・在学生

藤 晋一 FUJI Shinichi
教授 / 博士(農学)
生年月日 : 1967年1月30日
出身大学 : 新潟大学
Profile
- 専門
植物病理学
- 担当講義
(学部)植物病理学、植物保護学、害虫制御学、化学・生物学実験II、生物生産科学実験II、生物生産科学科研究室実験 (大学院)植物医科学、植物資源開発・管理科学
- Mail / URL
sfuji@akita-pu.ac.jp

戸田 武 TODA Takeshi
准教授 / 博士(農学)
生年月日 : 1975年1月28日
出身大学 : 岐阜大学大学院連合農学研究科
Profile
- 専門
植物病理学
- 担当講義
(学部)植物保護学、植物病理生態学、化学・生物学実験II、生物生産科学実験II、生物生産科学演習、生物生産科学科研究室実験 (大学院)植物医科学、植物資源開発・管理科学、共生生物学
- Mail / URL
ttoda@akita-pu.ac.jp

今 辰哉 KON Tatsuya
助教 / 博士(農学)
生年月日 : 1978年12月6日
出身大学 : 東北大学大学院農学研究科
Profile
- 専門
植物ウイルス学
- 担当講義
(学部)植物病理学、植物保護学、化学・生物学実験II、生物生産科学実験II、生物生産科学科研究室実験 (大学院)植物医科学
- Mail / URL
kon@akita-pu.ac.jp
- 博士前期課程1年
齋藤 唯人
佐々木 紘一
長森 郁哉
藤 皓貴
- 4年生
石川 周吾
伊藤 穂波
大山 美柚
佐藤 天都
鈴木 蓮太郎
- 3年生
鈴木 颯
慶伊 晃太
郷間 遥香
斎藤 彩汰
白石 悠
鈴木 麻央
徳光 恒太